出雲王朝を奉じる登美国蕃王 妹君に大国主命の后「御炊屋媛」がいる。
[私論編年 AD40~AD92、53歳で憤死]
 長髄彦の支配地は添下郡(現・奈良市)から城上郡(現・桜井市)それに河内に及んでいた。原大和王国(土着系)のこの王は、同時に山陰一体を治める先進的な出雲王朝(銅鐸文化圏)に帰服していた。ところが、一世紀中葉ヒムカ天孫族の勢力が北部九州に勃興、出雲国を直接脅かす動きに出た。そこで出雲の国の大王ニギハヤヒはAD70年ごろ、河内の哮
長髄彦の支配地は添下郡(現・奈良市)から城上郡(現・桜井市)それに河内に及んでいた。原大和王国(土着系)のこの王は、同時に山陰一体を治める先進的な出雲王朝(銅鐸文化圏)に帰服していた。ところが、一世紀中葉ヒムカ天孫族の勢力が北部九州に勃興、出雲国を直接脅かす動きに出た。そこで出雲の国の大王ニギハヤヒはAD70年ごろ、河内の哮 ヶ峰(たけるがみね/生駒山) に下り、ついで登美の白庭山 (現・登祢神社の付近:左の写真は同本殿) に宮を移してそれに備えた。長髄彦はニギハヤヒに臣下の礼をとって登美に迎え入れ、自らは河内の国を治めた。やがてAD86年ころ、神武東征が勃発、出雲王朝は丹波・因幡・伯耆・石見など各地の支援を得て、長期に亘る敵の攻撃にも持久戦で
ヶ峰(たけるがみね/生駒山) に下り、ついで登美の白庭山 (現・登祢神社の付近:左の写真は同本殿) に宮を移してそれに備えた。長髄彦はニギハヤヒに臣下の礼をとって登美に迎え入れ、自らは河内の国を治めた。やがてAD86年ころ、神武東征が勃発、出雲王朝は丹波・因幡・伯耆・石見など各地の支援を得て、長期に亘る敵の攻撃にも持久戦で よく耐えた。そうした中、神武軍は突如として向きを変えて難波の津へ押し寄せてきた。長髄彦は自ら軍を率いてこれを迎え撃ち孔舎衛坂(くさえのさか)で撃退した。そのおり退却する神武軍をあえて追撃せず、これが後々、長髄彦の命取りとなった。(左の鳥居は登美神社) ■ 一方、九州筑紫を本拠地とする神武の故国は、神武軍が河内敗戦・熊野退却・
よく耐えた。そうした中、神武軍は突如として向きを変えて難波の津へ押し寄せてきた。長髄彦は自ら軍を率いてこれを迎え撃ち孔舎衛坂(くさえのさか)で撃退した。そのおり退却する神武軍をあえて追撃せず、これが後々、長髄彦の命取りとなった。(左の鳥居は登美神社) ■ 一方、九州筑紫を本拠地とする神武の故国は、神武軍が河内敗戦・熊野退却・ 孤軍衰亡の危機をほぼ掌握していた。記紀神話風にこの状況を言解せば、アマテラスと高木神 (筑紫ヒムカの今は亡き大王) が夢枕に現れて建御雷(タカミカズチ)に〝私の御子たちが葦原中国でひどく悩んでいるので天降って平定しなさい〟と神託 (夢のお告げ)を された。 (左の円墳は富雄丸山古墳を遠望) ■ 建御雷(※ 1)は奴国を与る同大王家の忠
孤軍衰亡の危機をほぼ掌握していた。記紀神話風にこの状況を言解せば、アマテラスと高木神 (筑紫ヒムカの今は亡き大王) が夢枕に現れて建御雷(タカミカズチ)に〝私の御子たちが葦原中国でひどく悩んでいるので天降って平定しなさい〟と神託 (夢のお告げ)を された。 (左の円墳は富雄丸山古墳を遠望) ■ 建御雷(※ 1)は奴国を与る同大王家の忠 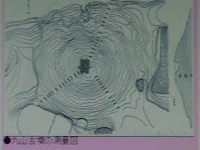 勇な臣下(外戚が降下したお身内であったか)で筑紫の護りに在って、その神託(切羽詰まった情報)を畏まって受け止め、椎根津彦に命じて救援に当たらせた。 (左の測量図は富雄丸山古墳) これによって息を吹き返した神武軍は、八咫烏を先導に嶮しい紀伊大台ヶ原を縦断、吉野から宇陀~磐余~葛城へと一気呵成に雪崩れ込んだ。長髄彦の支配地・城上
勇な臣下(外戚が降下したお身内であったか)で筑紫の護りに在って、その神託(切羽詰まった情報)を畏まって受け止め、椎根津彦に命じて救援に当たらせた。 (左の測量図は富雄丸山古墳) これによって息を吹き返した神武軍は、八咫烏を先導に嶮しい紀伊大台ヶ原を縦断、吉野から宇陀~磐余~葛城へと一気呵成に雪崩れ込んだ。長髄彦の支配地・城上  郡(現・桜井市)をも席巻、長髄彦の弟の安日彦(アビヒコ)はなすすべもなく散華した。■ 神武軍は、孔舎衛坂の戦いで一敗地にまみれたが、吉野越えからは手薄な宇陀を突き、情け容赦のない奇襲攻撃を展開した。山間僻地の俄か仕立ての安日彦のヘコ(兵)共では死に物狂いで襲いかかってくる尖鋭には刃が立たず侵入神武軍の蹂躙に為すすべもなく制圧された。
郡(現・桜井市)をも席巻、長髄彦の弟の安日彦(アビヒコ)はなすすべもなく散華した。■ 神武軍は、孔舎衛坂の戦いで一敗地にまみれたが、吉野越えからは手薄な宇陀を突き、情け容赦のない奇襲攻撃を展開した。山間僻地の俄か仕立ての安日彦のヘコ(兵)共では死に物狂いで襲いかかってくる尖鋭には刃が立たず侵入神武軍の蹂躙に為すすべもなく制圧された。
■ 神武侵入以前の原大和国の原風景は、幾つもの土豪たちが秩序ある集落(邑々を構成)を営んでいて、銅鐸文化を持ち込んだ出雲系弥生人とも同化・混血が進み、それが全体として均衡のとれたまとまりをみせ、東海北陸など遠隔地の国々とも盛んに交流が進みその社会的風土は比較的優しく争いごとの少ないのどかなものであった。(上の写真は、間近に見る富雄丸山古墳)
こうした温暖な気候風土と海の幸・山の幸に恵まれた豊葦原瑞穂の国は、新たな闖入者「筑紫ヒムカ族」によって不意を突かれ、あっと言う間にその一角を蹂躙され占拠されてしまった。長髄彦は切り裂かれた地・捕らわれた高貴な姫君たち、それらを奪還すべく神武に挑むが勝敗は決せず ついに大和川を挟んで南にイワレヒコ・北にニギハヤヒが直接対峙する局面が出現した。
■ 兇賊イワレヒコ軍に脾臓のごとき地を突如として突かれ孫娘(出雲王朝の皇女)二人を奪われた。蕃王ナガスネヒコはその敗戦の責を問われ死を賜った。しかもこともあろうにナガスネヒコの甥の宇摩志麻治に処断させるというまことに痛ましい結末を辿った。憤死したであろう長髄彦の塚は当時築くことが憚られ、宇摩志麻治の後裔の登美連らの代になってから漸くその築造が許され、その祟は鎮められた。その古墳は被葬者の名が今もって謎とされている富雄の丸山古墳ではなかったか!。同丸山古墳は、直径86m=高さ10.5m 近畿では最大規模の円墳だという。この墳墓こそ長髄彦王に相応しい異質の王陵なのである。
■ 序でに申せば登祢神社は本来、長髄彦命を主祭神として祀る隠された奉斎神社であると私は観る。また城上郡の等祢神社はその弟の安日彦命(アビヒコ)を主祭神として弔うこれまた隠された奉斎神社であろうと思う・・。
(板厚30ミリ)
(※ 1) 「建御雷」の亦の名は「天押雲」、亦の名は「帥升」という異名同人である。建御雷は記紀神話に出てくる名、天押雲は中臣氏の系図に出てくる名、帥升は漢書に出てくる名、何れも名こそ違え同時代同立場の同一人物である。因みに魏志倭人伝に出てくる「難升米」は中臣氏の「梨迹臣」である。天押雲から数えて五世孫でもある。
長髄彦王とは、ヤマト王権発祥の地で、その淵源に深く関わり、そして消えていった「原大和王国」最後の王であった。憂国と憤怒の念を懐きながらも最期は一身に全責任を被り粛然と死に赴いていったこの王に対して、私は私なりに深く哀惜と畏敬の念を表しつつ、ここに祈りの作品を奉げた。
2012/12/19 著作者 小川正武








